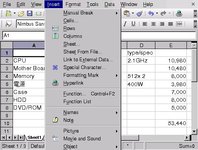|
#1
[pkgsrc] ja-freewnn-lib DESTDIR_SUPPORT
inputmethod/ja-freewnn-lib
inputmethod/ja-freewnn-server
inputmethod/ja-freewnn-dict
が
PKG_DESTDIR_SUPPORT= user-destdir
になっていないので、直す必要がある訳で、
ちょっと日和って、次の二つにするのを提案中な訳だけれど、
wip/ja-freewnn-lib
wip/ja-freewnn-server
それで、これを commit すれば良いという話にはなっていて、
以前の Q2 freeze の前に、(時間がなくて)あきらめた経緯がある。
さて、もう次の Q3 freeze が来てしまった。
以前には、やるべきことは ChangeLog の要約を作って commit message
とする、ということだったけれど、
(以前に pkgsrc に変更された時からの) 間が長いので、これがある意味面倒。
ChangeLog ChangeLog.en Changelog.old を眺めたりしているけれど、.old は
時期的に関係ないとして... ChangeLog は最初が英語で途中から日本語になる。
ChangeLog.en は、その途中から日本語になったものの一部を更に翻訳した
形になっている。
良く考えると、上記 wip/ja-freewnn- 版は、更に patch を追加して a-022 版
相当になっている。それのことも含める必要がある。
以前に、かなり長い Commit message を入力したら、joerg に長すぎると言われ
たこともあり、結局 commit message は何か短くすませれば良いと思ってはいる。
さて、実際の cvs 操作はどうするのかな、とちょっと思案中
dict + lib -> lib という形になるので、dict 側は削除すれば良いのかと思われる。
wip の TODO に commit message の長いものを書いておいて、添削して短くして
それを最後に使う、という案を考え中
ChangeLog 1999-07-19 to 2005-11-30, 1.1.1-a001 to 1.1.1-a021
(2003-09-16 to 2005-11-30 in English)
(1999-07-19 to 2003-06-16 in Japanese)
ChangeLog.en 2001-05-19 to 2005-11-30,
partly translated ( part of a020 to a021)
ChangeLog.old (1999-03-20 to 1999-05-14, Before FreeWnn Project)
今の inputmethod/ja-freewnn-lib は 1.10 で pkgsrc 的には
2002/05/31 の更新、あるいは 2002/06/10 の patch-1.1.0-a01.gz が最後
ChangeLog には 1.1.1-a0xx の(内部公開的な)名前が入っているが
ChangeLog.en には、その名前が入っていない。
ChangeLog によれば、
patch-1.1.1-a001 は 1999-07-19 になっている。pkgsrc には、
これも入っていなかったのかな。
patch という形でしか出ていなかったのか、それとも内部公開だったのだろうか。
それとも、こんな簡単な形で:
- bump to 1.10 to 1.1.1-a021, See ChangeLog, ChangeLog.en (too many lines to list here)
- Add more, a021 to a022 (CVS version) equivalent patches
- DESTDIR support (That's why a022 patches added)
- package structure adjusted from (-lib -dict -server -server-bin) to (-lib -server) for minimum modification from DISTFILE to pkgsrc.
@
共通部分を作って、あとは file by file:
commit message だけれど、全部に使える長いものを作って、
全てに使うという方法がないでもないが、そうすると、patch
なんか沢山あってまとめて cvs log すると、多分すごくうるさくなる。
そこで、共通部分を(上のくらいに)作文して、後は、file by file
で変更点を書いておく(のかな) それはそれで大変なのだけれど。
@
commit はしましたが、:
二回間違えました。一回目は自分の mirror 保管庫に commit してしまった。
これは特に問題にはならないですが、まだ commit していないのに commit しました
メールを書いてしまった。
二回目は譜が不足していました。例によって obache さんが直して下さいました。
(一度、空のところで cvs update して確認する必要がありますね)
それで、関係先として、
kinput2 は直したつもりなのだけれど editors/mule も関係があった。
Dumping under names emacs and emacs-19.28.1
./temacs -batch -l /export/pkgsrc/editors/mule/work/mule/src/
../lisp/mule-inst.el /export/pkgsrc editors/mule/work/mule/src/../lisp/quail/[a-zA-Z]*.el
Warning: arch-dependent data dir (/usr/pkg/lib/mule/19.28/i386--netbsd/) does not exist.
Loading /export/pkgsrc/editors/mule/work/mule/src/../lisp/mule-inst.el...
./emacs -batch -l /export/pkgsrc/editors/mule/work/mule/src/../lisp/mule-diag.elc -f dump-charse
gmake[1]: *** [../etc/charset] Segmentation fault (core dumped)
gmake[1]: Leaving directory `/export/pkgsrc/editors/mule/work/mule/src'
gmake: *** [src] Error 2
*** Error code 2
こんな感じ。以前からなのか、今回の変更によるのか一応不明。多分前者の気がする。
やはり bulk build から統計を表示する道具があるといいなと思う。
@
core の stack dump:
(gdb) bt
#0 0xbb47fcf7 in kill () from /usr/lib/libc.so.12
#1 0x08084049 in fatal_error_signal (sig=11) at emacs.c:225
#2 <signal handler called>
#3 0x080b60f4 in make_uninit_string (length=44) at alloc.c:933
#4 0x080b6231 in make_string (contents=0xbf7ff1de
"TIMEFMT=%U %S %*E %P %X+%Dk %I+%Oio %Fpf+%Ww", length=44) at alloc.c:912
#5 0x080b6278 in build_string (str=0xbf7ff1de
"TIMEFMT=%U %S %*E %P %X+%Dk %I+%Oio %Fpf+%Ww") at alloc.c:921
#6 0x080daa0f in set_process_environment () at callproc.c:1228
#7 0x08083957 in main (argc=6, argv=0xbf7fdf70, envp=Cannot access memory at address 0x8
) at emacs.c:722
(gdb)
#1
[pkgsrc] OpenOffice -> scalc column(行と列)
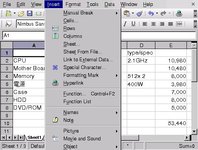  しばらく前に作った しばらく前に作った
OpenOffice
(openoffice2-2.2.1)
を使って見た。scalc あるいは scalc be2350.ods
のように起動する。なかなか良く出来ている気がする。
実は、この機械は AMD で、今は NetBSD/i386 で動いているが、
NetBSD/amd64 だとだめなのかも知れないという気がして来た。
良く出来ていると思った一つは、Insert の選択の中に Rows と Columns があるけれど、
それに図が付いているということ (右側の図、クリックで拡大します)。まあ、これ自体は大したこと
ではないかも知れないが Row と Column は米国人でも混乱するのかということが分った。
普通 Column って何 ? と聞くと、たいていの人は横長の箱を思いうかべると思うが、
Column とは柱で、この選択肢の図にあるように縦長が正しい。
英和
で column を索くと最初に出て来るのは柱だ。
和伊辞典に御相談したら、柱 → (円柱) colonna(女)と書いてある。
Column は横長だと思っている場合、例えば HTML でも colscan と言えば、横にのばす
ことだけれど、それは column の数は横に進むからである。
column(柱) を並べて、それに番号を付けて、
その番号を見ると 1 2 3 4 と横に進む訳である。言い直せば、その(柱 = 横長)という
理解は column
ではなく column number のことを言っていることになる。
左側の図で言えば A B C D が column の名前ということになる。確かに A B C D は横に伸びている。
横書き社会でもこれだから、日本語になるともっと厄介。column = 行 となって縦か横か
良く分らない (row は 列)。でも column に行の訳を付けたのは日本の勝手か。縦か横か分らな
い訳を当てたツケは高くつくということかな。
という訳で、Insert の columns と rows に図の説明が付いている OpenOffice の scalc は素適
ということになった。
@
Prime A Regulus (BE 2350):
で何の計算をしているかと言うと
dos/v paradise に
Prime A Regulus
という BE 2350 の機械がある。基本は 42,980 円。
お店で聞いて見ると、通常一年の保証が付くが、Windows XP か Vista でないとその保証は付かない、
という話であって、じゃ自分で組合せたらいくらで出来るかを
計算して見た
(ただし Mother Board は全く同じではないし、
Memory など増してあるので基本とそのままで比べられない)。
@
他に何が出来るのかな:
| 起動名 | 種別 | MS 名 |
|---|
| swriter | 文書作成 | Word |
| soffice | 総合入口 | Office |
| simpress | 発表資料 | PowerPoint |
| sdraw | 図作成 | Visio |
| scalc | 表計算 | Excel |
unopkg
#1
[NetBSD] ./build.sh -m newsmips -a mipseb tools
libtool: link: cannot find the library `'
何か間違えているかな ...
138 20:00 cvs update -D '20060906 00:00-UTC'
139 20:35 ./build.sh -m newsmips -a mipseb tools
159 22:03 cvs update -D '20060905 00:00-UTC'
160 22:04 cvs update -D '20060822 00:00-UTC'
161 22:28 ./build.sh -m newsmips -a mipseb tools
144 21:41 cd /export/20060906/src/tools/binutils/obj/build/bfd
145 21:41 /bin/sh
/export/20060906/src/tools/binutils/../../gnu/dist/binutils/bfd/../move-if-change
tofiles ofiles
146 21:41 /bin/sh ./libtool --mode=link cc -W -Wall
-Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -O -o libbfd.la
-rpath
/export/20060906/src/tooldir.NetBSD-4.99.1-powerpc/powerpc-unknown-netbsd4.99.1/mipseb--netbsd/lib
-release 2.16.1 archive.lo archures.lo bfd.lo bfdio.lo
bfdwin.lo cache.lo coffgen.lo corefile.lo format.lo init.lo
libbfd.lo opncls.lo reloc.lo section.lo syms.lo targets.lo
hash.lo linker.lo srec.lo binary.lo tekhex.lo ihex.lo
stabs.lo stab-syms.lo merge.lo dwarf2.lo simple.lo
archive64.lo `cat ofiles`
先日の perl の問題と同じ根 ?
#1
[Mail] mx backup と smtpfeed
mail の mx を次のように設定していたとします。
10 mail.example.com
20 backup.example.com
つまり 普通なら mail に、また mail が利用出来ない場合には backup
に送るようにしているとします。MTA は sendmail を想定しています。
ここで backup 側に
smtpfeed
を加えていたとします。
で、mail が落ちていた場合に、何が起きるか、です。
メールは backup に送られます。受取ったメールは smtpfeed に無条件
に渡されます。smtpfeed は mail に送ろうとするのですが、
Sep 13 05:59:55 backup smtpfeed[3328]: NOID: 1/4: getpeername failed for mail.example.com: Socket is not connected
と言って、送れません。送れなかったメールはどこに行くのでせうか ?
(変だなぁ、それがもし捨てられてしまうとすると、Mailing List は運用出来ないことになる)
-m fallbackmx Fallback MX 先の指定 (デフォルトは指定なし)
すべての MX が応答しなかった場合や DNS が引けなかった場合に、
これって
smtpfeed の説明
かな ?
(orange.kame.net)
(インストールの方法)
(fkimura.com)
10 mail.example.com
20 nosmtpfeed.example.com
30 backup.example.com
としておけば問題がないということかな ? そう出来ない時には
Msmtpf, P=/usr/local/libexec/smtpfeed, F=mDFMuXz,
S=EnvFromSMTP/HdrFromSMTP, R=EnvToSMTP,
T=DNS/RFC822/SMTP, r=100,
A=smtpfeed -l local5 -V -n 255 -E -m nosmtpfeed.example.com
のようにする ? (同じことか)
メール配送と、mx Fallback とを混乱しているという気はしているが。
何とはなく「mx Fallback の機械には smtpfeed は使わないこと」の気がする。
更新: "2004/09/25 22:36:14"
ttyp2:makoto@harry 23:46:53/040912(...checkout/src)> time sudo ./build.sh -u release > & ../log-simple-gcc-replace-u-MKGCC=yes
8276.995u 1895.504s 3:03:52.57 92.2% 0+0k 1003+240606io 21704pf+188w
cc -O2 -pipe -Werror -Wall -Wpointer-arith -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wno-uninitialized -Wno-main -Wno-format-zero-length -Wno-nonn
ull -msoft-float -fno-zero-initialized-in-bss -ffreestanding -I. -I/export/20040822/checkout/src/sys/arch -I/export/20040822/checkout/src/sys -nostd
inc -DDIAGNOSTIC -DMAXUSERS=32 -D_KERNEL -D_KERNEL_OPT -Dmacppc -c /export/20040822/checkout/src/sys/kern/kern_sa.c
/export/20040822/checkout/src/sys/kern/kern_sa.c: In function `sys_sa_setconcurrency':
/export/20040822/checkout/src/sys/kern/kern_sa.c:546:
error: `CPU_INFO_ITERATOR' undeclared
(first use in this function)
~
*** Failed command: cc -O2 -pipe -Werror -Wall -Wpointer-arith -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wno-uninitialized -Wno-main -Wno-format-zero
-length -Wno-nonnull -msoft-float -fno-zero-initialized-in-bss -ffreestanding -I. -I/export/20040822/checkout/src/sys/arch -I/export/20040822/checkou
t/src/sys -nostdinc -DDIAGNOSTIC -DMAXUSERS=32 -D_KERNEL -D_KERNEL_OPT -Dmacppc -c /export/20040822/checkout/src/sys/kern/kern_sa.c
*** Error code 1
Stop.
nbmake: stopped in /export/20040822/checkout/src/sys/arch/macppc/compile/GENERIC.MP
I got
the error
very recently, which I do not remember at all ;-(
#2
[機械] 件の Celeron 君に pivot を入れたら、
勝手に再起動するようになってしまって使いものにならない。
で、
の中の一番安いのを買って来た。本当は、
Prime Knight
にしたかったのだけれど、何故かお店の人が勧めないのので、安い方に
にした。 37,800 円 + 1,500 円 (20G -> 40G) = 39,300 円。
AGP さえ付いていない安いもの。
オンボード VGA というのが何なのか分っていなくて、800x600 16 色なので
例によって余った nVDIA のカードを刺す。
前の機械の時は、driver をどこからか探して来たのだけれど、今回は
ただ刺しただけで、設定してくれた。plug & play おそろし。
これに Win2k/Pro + Office2k/Pro + pivot で快適。
pivot
ってとてもいいと思うのだけれど、多分使っている人は少ないのだろうなぁ
(現在 30 日間無料期間中)。今は CRT を横に倒して使っている。
#1
[Network] ICMP/Fragment Reassembly Time Exceeded
より:
Fragment Reassembly Time Exceeded
ICMP sender (destination host) did not receive all fragment parts
before the expiration (in seconds of holding time) of the TTL value of
the first fragment received.
これ良く分らない文。
「最初の断片を受取った時の TTL の値 の有効期限(秒表示)より前に
全ての断片化パケットを受取れなかった時」
今回の場合、相手からこれを言われているということは、要するに
「こちらから送り出した断片の全ては、(時間内に)届いていない」
ということだ。
If a host reassembling a fragmented datagram cannot complete the
reassembly due to missing fragments within its time limit it
discards the datagram, and it may send a time exceeded message.
- 送り出しの TTL が小さすぎる
- 断片の一部が届いていない
のどちらか。
@
net.inet.ip.ttl = 64:
現状は
ttyp1:makoto@gateway 7:57:46/020913(/home/makoto)# sysctl -a |grep ttl
net.inet.ip.ttl = 64
試しに 128 にして見る。(いいのかなぁ)
net.inet.ip.gifttl = 30
これは何 ? gif って IPv6 用の tunnel i/f のようだ。(今回関係なし)
08:04:27.142175 PPPoE [ses 0x98b3] *-*-206-61.hoge.jp > n.ki.nu: icmp: ip reassembly time exceeded
が出るので、更に 192 にして見る。
08:04:51.142168 PPPoE [ses 0x98b3] *-*-206-61.hoge.jp > n.ki.nu: icmp: ip reassembly time exceeded
まだ出るので、そういう問題ではないか。
@
DF=1 Don't Frag を立てて送り出しているはず:
なのに、Frag しているというのは何故 ? これはこちらの問題。
(もしかして立っていない ?) server で
net.inet.ip.mtudisc = 0
あれーっ。
makoto@milano 8:14:34/020913(...log/httpd)# cat /etc/sysctl.conf
net.inet.ip.mtudisc=1
なのに何故。多分五日前に再起動した時からこうだったのだろう。
8:14AM up 5 days, 22:52, 2 users, load averages: 0.75, 0.32, 0.22
8:18 分頃変更。
という訳で、問題は
@
Frag した packet がどこかで捨てられてしまうこと:
net.inet.ip.mtudisc = 0
で送り出した場合、こちらの NetBSD/gateway で断片化されるが、
それが相手側でうまく組立てられない。... 何故。
なので、
@
DFbit=1 で送り出しておけば、多分問題は避けて通れる。:
(なのに、今回それが外れていた)。
さて、
ping -s 1992 *-*-206-61.hoge.jp
すると通らない。frag している。ping には DFbit が効かない ?
(そんなはずはなさそう)。
どちらにしても ping には答えないようだが、それはいいとしよう。
から下へ。ありがとうございます。何はともあれ良かった。
otsune さんのアンテナ
にも
(遅くても 9:22 には)
見えているので、多分こちらも同じ問題だった気がする。
うちの送り出しの Fragment は (mtudisc=0 の時の話として)
上の
FreeBSD/ipfw and fragment packet の man
の記述を満たしているのだろうか
(日本語としては、「満たさないようになっているのだろうか」かも知れない)。
「昨日の件は当てはまらない」かどうか、僕は理解していない (ごめんなさい)。
#3
perl の s/.../.../s は何だっけ
perldoc perlop して modif で探すと
If the "/s" modifier is specified,
sequences of characters that were transliterated
to the same character are squashed down to a sin-
gle instance of the character.
いくつも同じ文字が続く時は、
一つの文字としてまとめて(squash)しまう
if ($$contref =~ s!<TITLE[^>]*>([^<]+)</TITLE>!!i) {
if ($$contref =~ s!<TITLE[^>]*>([^<]+)</TITLE>!!is) {
レモンスカッシュか。
#2
[Namazu] namazu-2.0.7 が出た。
もっと日本語修正
も作った(直した)が、ちょっと例を採集する時など、
英語版 mknmz: /tmp/yy: invalid output directory
普通の日本語 mknmz: /tmp/yy 無効な出力ディレクトリ指定
もっと日本語 mknmz: /tmp/yy: 無効な出力目録(位置)指定
と切換えられた方がいいという気がして来た。
上記例は /tmp/yy がない時にもこういうので少し不親切だと思う。
#1
[CVS] info -> cvs init
何故か
cvs
の使い方を見ている。
cvs init について知りたいと思ったが、info で探すのに時間が
かかった。
一番初めから「空白」を押して行くと
Menu
Overview
What is CVS
What is CVS not?
A sample session
Getting the source
Committing your change
Cleaning up
Viewing differences
The Repository
....
Creating a repository
のように行けるが、実は後から見れば、簡単で、
Menu
-> (2) The Repository
-> (6) Creating a repository
で行ける (でも cvs init は、最初に書いて欲しい気もする)。
確かに cvs を最初に使う人が、
- 人の用意したものをまず使う (お客様 = user)
- 自分で用意する (管理者 = administrator)
のどちらかと言えば、前者かも知れないが、だったら、
その前に、
- 既にある保管庫(Repository) をどこかで見つけて来る
- なかったら自分で作る (その時は先を読んでね -> cvs init)
という説明が欲しい気もする。
@
cvs -d /usr/local/cvsroot init:
でその info の画面の中に
cvs -d /usr/local/cvsroot init
という例があるが、
僕の理解は、cvs init は $CVSROOT を見ないのではないか
ということ。
でも
「バージョン管理システム(CVS)の導入と活用」
の p42 にはそのようには書いていなくて
mkdir $CVSROOT
cvs init
だけがまず書いてある。僕が使っているのは NetBSD に付いて来た
Concurrent Versions System (CVS) 1.11 (client/server)
というやつ。いまもう一度試したら参照した。変。
これは、どうも現目録(current directory)にある ~/.cvspass のせいらしい。
makoto@u ■12:59:16/010913(~)> cvs init
cvs [init aborted]: connect to a.ki.nu:2401 failed: Connection refused
makoto@u ■12:59:22/010913(~)> cvs -d $CVSROOT init
makoto@u ■12:59:29/010913(~)>
4462歩
アップル・ストアでは受注しているようだ。
サーバ用に、以前のものを一番安く買うか、それとも持運び用に
一番速いものにするか。
Graphite だと、今あるのと区別が付かない。Key Lime だと下位機種
と区別が付かない。
しかし軽くはなっていないようだ。VRAM が 4 -> 8 MB に増えている。
Firewire も今までは付いていなかったのかな。
MHonArc っていま考えると良く出来ていると思う。
参照関係を見てつないで行くところが一番素晴しい。
僕は、次のようになっているものにいくつか追加したいものがある。
Subject
From
Date
例えば X-Mail-Count: とか。
でもその方法がまだ分っていない。
jitterbug.c
の
static char *getsubject(char *mbuf)
の中を変更する必要がありそう。
@
http:// の hypertext 取扱:
次のように戻すと一応直るが。
--- making/jitterbug-1.6.2.i18n/source/jitterbug.c-oo Sun Sep 26 23:00:55 1999
+++ making/jitterbug-1.6.2.i18n/source/jitterbug.c Mon Sep 11 13:51:19 2000
@@ -227,7 +227,7 @@
p = s + strlen(url_markers[i]);
while ((*p) &&
-#ifdef I18N
+#ifdef 0
(
#else
(isalnum(*p) ||
#1
[NetBSD] macppc Open Firmware が電源投入時に初期化しない問題
|